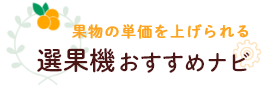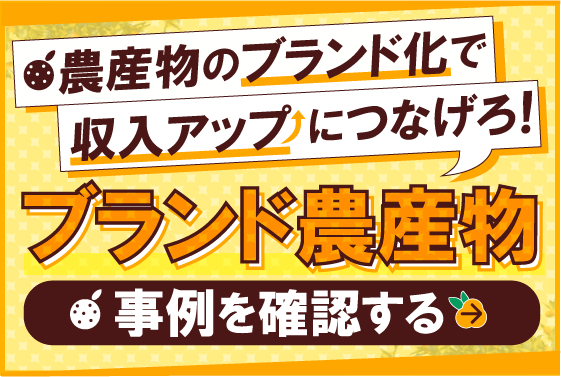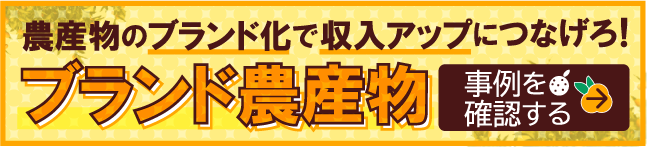卸業者を通さずに売る
野菜や果物の販売経路が多様化し、出荷組合や卸業者を通さずに消費者と直接やりとりする方法で利益向上を成功させている生産者も増えています。そのほうが高く売れるの?トラブルが発生する可能性は?そんな、卸業者を通さずに野菜や果物を売るメリット・デメリット、注意点などを紹介します。
出荷組合や卸業者を通さないメリット
市場に左右されない価格設定が可能
JAなどの出荷組合や卸業者を通して果物を販売する場合、農産物の価格は市場価格と等級、階級によって決められており、自分でコントロールはできません。出荷時にすら価格を把握できず、後で結果を知らされる仕組みです。
消費者と直接やりとりできる方法をとれば、逆に自由な価格設定が可能。利益が増えるように調整できます。
中間コストに利益をとられない
出荷組合、卸業者、仲卸業者、小売店と、一般的には消費者の手に届くまで多くの企業を通すと、それぞれで手数料が発生し、利益が下がります。
直売所を利用すると、各組合や業者に依頼する経費がなくなり、直売所の事務手数料だけになるため、経費は4分の1以下になることも。同じ値段で売り出したとしても、直売所で販売するほうが3倍以上利益が高まるケースがあるのです。
農産物のブランド化がしやすい
出荷組合や卸業者で取り扱う野菜や果物は基本的には決まっているため、それ以外の珍しい農産物を引き取ってくれない可能性が高いです。取り扱いがあったとしても、例えば無農薬で作ろうが、糖度を高くしようがあまり関係なく、均一な規格内に野菜や果物をおさめるので差別化することはできません。
地域でブランド化に成功している事例もありますが、個人のこだわりがブランドに反映されてのものではありません。自分のこだわりを商品に反映して、ブランドとして顧客に届けるには卸業者を通さない方法が適しています。
生産者が卸業者を通さないで売るデメリット
販路や配送業者の確保が必要
卸業者に出荷をする場合は、販路を自分で確保する必要がなく、卸業者に納めれば値段はつきます。納めた後は卸業者が市場でさばいてくれますし、配送なども全てお任せです。
自分で販売をする場合はもちろん販路は自分で探す必要があります。また見つけた販売先への配送なども、自ら配送するか、業者を探さなくてはいけません。
ただ、最近は物流のIT化も進んでいるため、集荷などスマホで簡単に依頼できるなど以前と比べるとデメリットは減ってきています。
配送よりも販路の確保が、大きな違いになるでしょう。
大量の農産物はさばけない
個人で卸業者ほどの量を対応するのは限界があるでしょう。
卸業者の場合は出荷先が市場になるので、規格内のものであれば、ほぼ制限なく引き取ってもらえます。一方、自分で販売をするのであれば、そうはいきません。大手スーパーのチェーン店やファミレスなどと直接契約ができたとしても、市場と比べると出荷できる量は制限されます。
出荷組合や卸業者を通さないで販売するデメリットを回避するには、量ではなく値段で勝負したり、卸業者と掛け持ちするなど工夫が必要です。
生産者が卸業者を通さないで売る方法
卸業者を通さないで野菜や果物を販売する方法は、ネット販売や道の駅といった直売所での販売の他、小売店や飲食店などへの直接販売があります。
直接の売り先として考えられるのは、スーパーや八百屋などの小売店、ファミレス、ラーメン屋などの飲食店です。販売するには直接営業を行う必要もあるので注意してください。自分の農園の近くの小売店や飲食店をリストアップするところからはじめるのがおすすめです。
生産者が卸業者を通さないで売る際のポイント
卸業者を通さないで売る際のポイントは、「商品の差別化を図り、品質に応じた正当な値づけ」「量にだけに頼らない販売」「物流費をいかに押さえるか」。直販売のメリットを活かして、デメリットを克服することを意識することです。
こだわりの野菜や果物の価値を理解してもらえる売り先を、できれば近いところで確保するのが理想。そのためには商品のブランド化がポイントになります。
大切なのはブランド化
JAをはじめとする出荷組合や、卸業者を通さないで売る際に大切なのは、野菜や果物のブランド化(差別化)です。
スーパーなどの小売店は、市場から規格品の野菜を安く入手するルートが既に確立しているので、普通の野菜であればあえて個別で生産者から直接仕入れるメリットはありません。そこでブランド化が鍵になります。
例えば「糖度10度以上のトマトだけ選び抜いた」とか、「超大玉3Lサイズのマンゴーのみ厳選」などと差別化を図りましょう。「地元産」「生産者の顔が見える」「有機農法」といった付加価値もブランド化につながります。
また生産者側での戦略だけでなく、つくっている農産物の品質管理や品質の高さの見える化も大切。これは最近注目を集めている光センサー式の選果機の利用がおすすめです。
内部の品質を検査し、不良品のない一定以上の品質を確保すること。糖度や熟度を測り、品質(美味しさ)を見える化することで、選ばれる果物にできるでしょう。