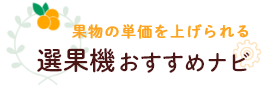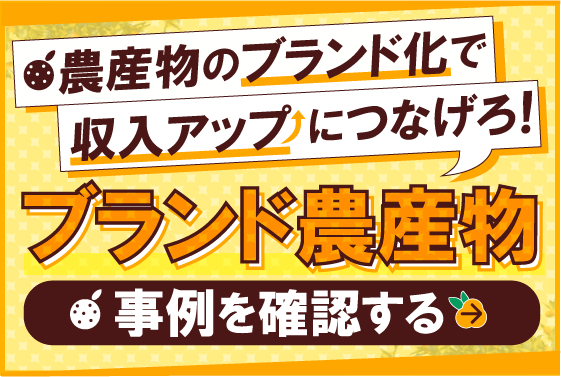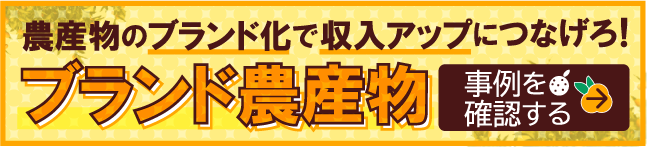道の駅で売る
道の駅や農産物直売所での直接販売は、大きな販路の1つです。都市農山漁村交流活性化機構の調べによると、全国の直売所の数はおおよそ23,000店舗、年間販売額1兆円の規模を誇ります。
(出典:一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構「農林資産物直売所・実態調査報告」2018年11月)
そんな道の駅や直売所で販売をするメリットやデメリット、販売方法や注意点を解説します。
道の駅・直売所で売るメリット
自分で価格を決められる
道の駅や農産物直売所で販売するメリットは、農家自らが価格を決められることです。出荷団体や卸業者を通す場合、単価は相場に大きく依存するため、自分でのコントロールができません。
需給バランスに左右されますので天候が良いときなどは、価格が大幅に下落するリスクもあります。
一方、直売所では相場の影響を受けにくく比較的高い利益率を維持することが可能です。直売所への販売手数料は一般的には15%程度で、卸業者をはさむよりも手元に残るお金は多くなります。
ブランドを打ち出しやすい
道の駅や直売所での販売は、自分の名前で野菜や果物を販売することになるため、ブランド化してファンを増やしやすい体制。栽培方法へのこだわりや思い、品種の魅力や栽培理由など「顔の見える野菜や果物」をアピールできます。
また、直売所では消費者からの反応をよりダイレクトに感じられるため、ニーズをくみ取って新しい品種を導入することもできるかもしれません。生産へのモチベーションが上がるのも隠れたメリットの1つでしょう。
道の駅・直売所で売るデメリット
競争が激しい
価格コントロールをしていない直売所では、価格競争が激しい傾向にあります。生産者自身で価格のコントロールができる分、安値合戦になることもしばしば。
直売所では現役を引退して、趣味の一貫として農業をやっている世代もおり、安値では勝てないケースも多くあります。直売所の価格方針を事前に確認しておくことや、差別化を図ることが大切です。
包装や出荷も自分の仕事
中間業者をはさまないため、スーパーや市場へ卸すまでに必要な包装・出荷も生産者自身が対応することになります。売れ残った場合の商品の回収や、代金の回収も自分で対応しなくてはなりません。
商品が安定的に売れないと、直売所で販売する手間やコストの負担のほうが大きくなる可能性があります。継続して購入してもらえる品質やブランド力が大切になります。
道の駅・直売所で売る方法
基本的には各直売所での判断となりますので、直接問い合わせをする必要があります。ほとんどの場合、組合員になる必要があり、入会金や運営費の支払いが発生するので要注意です。
加工をせず、野菜や果物をそのまま販売するだけなら、特別な申請などは必要ありません。各直売所の指示に従い、出荷しましょう。売値の15%の出店手数料が発生すると考えておくのがおすすめです。
農園を持っている生産者であれば出店は難しくはありませが、地元優先など、直売所ごとにルールがあるのでこちらも直接確認してみてください。
道の駅・直売所で売る際のポイント
道の駅で売る際のポイントは、差別化とリピーターを獲得することです。JAへの出荷と道の駅などの直売所で農産物を販売する違いは、オリジナリティを出せること。
例えば「農産物へのこだわりをテロップにして書く」「顔写真をつける」「食べ方の案内をつける」といった工夫ができるのは、直売所ならではです。
オリジナリティのある農産物で差別化をはかって覚えてもらったら、次はリピーターの獲得を。リピーターになってもらうには差別化はもちろんですが、作物の品質がモノを言います。
大切なのはブランド化
道の駅や直売所で安定して売り上げを上げるには、農園や農産物のブランド化が大切です。近年、農業を営む新規参入者が増えており、農産物のブランド化におけるマーケティングの重要性が注目される機会が増えてきました。
ただし、農産物のブランド化や販売において最も大切なのは品質への信頼ということを忘れてはいけません。まずは農産物の「安定的な品質」という土台を確保して、顧客の信頼を得て、それから諸々の施策を実施してブランド化を目指しましょう。